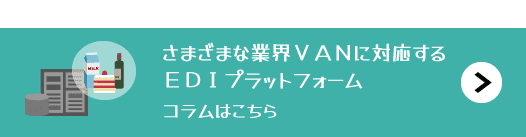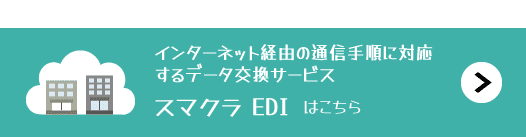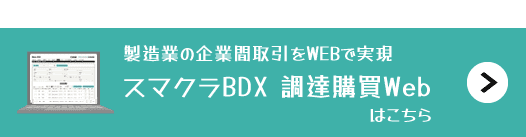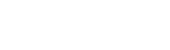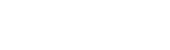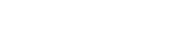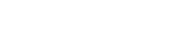EDIの種類は?EDIを分かりやすく説明「EDIガイド」

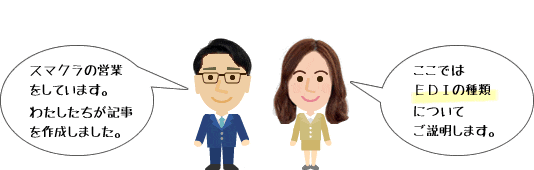
EDIは、企業間取引を電子化し、受発注や請求などの業務を効率化する仕組みです。しかし、EDIには複数の種類があり、特徴や導入コスト、運用方法が異なります。
ここでは、標準EDI・業界VAN・個別EDI・インターネットEDI・Web-EDIなど、代表的なEDIの種類とそれぞれの特徴をわかりやすく解説します。自社に最適なEDI方式を選ぶための参考にしてください。
1.EDIの種類と分け方は?
EDIにはいくつかの種類があり、その違いを知っておくことは大切です。ここでは、押さえるべきEDIの分け方と種類について説明します。
EDIには代表的な分け方としての3つの種類 「(業界ごとの)標準EDI」「業界VAN」「個別EDI」があります。
次に、通信手段(固定電話、インターネット)による分け方では「レガシーEDI」「インターネットEDI」があります。
さらに、インターネットによるEDIには「Web-EDI」「インターネットEDI」があります。
2.業界ごとの標準EDIとは?
標準EDIとは、業界ごとに制定されたルール(規約・規格)に従って、標準書式の見積書や注文書などのビジネス文書を企業間でやり取りする、通信回線を用いた電子商取引の仕組みのことです。
業務効率化、コスト削減、迅速な情報共有、データの正確性向上、取引先との関係強化などのメリットがあります。
代表的なものとして、製造業界の「ECALGA」、流通業界の「流通BMS」、中手企業向けに簡易化された業界汎用の「中小企業共通EDI」があります。
| 製造業界向け標準EDI 「ECALGA」 |
ECALGA(Electronic Commerce ALliance for Global Business Activity)は、JEITA/ECセンターが標準化、実用化を推進している次世代EC標準の総称です。 そのコンセプトは、「全ての壁を越えて、全てのビジネスプロセスをグローバルかつシームレスに繋ぎ、ダイナミックなビジネス展開を可能にするビジネススタンダード」です。 ECALGA対象の通信プロトコルには、ebXML手順、拡張Z手順などがあります。 JEITA/ECセンターURL:https://ec.jeita.or.jp/ |
|---|---|
| 流通業界向け標準EDI 「流通BMS」 |
流通BMSは、流通ビジネスメッセージ標準の略で、通信手段にインターネットを利用しています。 小売と卸、メーカーの取引を電子化するためのルールです。取引業務の効率化と高度化を目標に、業界ぐるみで、その策定と普及・導入が進められています。 流通BMS対象の通信プロトコルには、JX手順、ebXML手順、EDIINT AS2手順があります。 流通BMS協議会URL:https://www.gs1jp.org/ryutsu-bms/ |
| 中小企業向けの標準EDI 「中小企業共通EDI」 |
中小企業共通EDIとは、ITの利用に不慣れな中小企業でも、簡単・便利・低コストに受発注業務のIT化を実現できる汎用性の高い仕組みです。 中小企業庁URL:https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/gijut/edi.html |
3.業界VANとは?
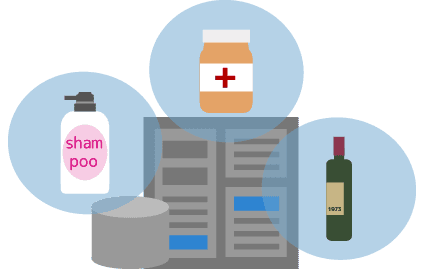
業界VANとは、特定の業界に特化したネットワークサービスです。
プラネット(日用品業界VAN)やハウネット(家庭用品・食品軽包装業界VAN)、ファイネット(酒・加食業界)、JD-NET(医薬品業界VAN)などが業界VANの例として挙げられます。
業界VAN接続に対応した導入事例はこちらをご覧ください。
大手菓子製造販売会社4.個別EDIとは?
個別EDIとは、データ交換の形式やフォーマットが取引先毎に取り決められたEDIです。
カスタマイズの自由度が高く、取引先ごとに専用システムを構築できるため、取引先が少ない場合に適しているといえます。
一方、取引先ごとに専用システムを構築することは、取引先が多い場合には効率が悪いという欠点にもなり、多く取引先を持つ場合には不向きです。
また、発注者主導でルールが決まることが多いため、個別EDIで得意先と取引する受注者は、いわゆる多画面問題(得意先ごとに画面表示やレイアウトなどが異なり、運用に手間がかかる問題)により運用負担が増える傾向にあります。
5.レガシーEDIとインターネットEDIとは?
現在のEDIは、通信回線にインターネットを用いた電子データ交換が主流で、これを一般的に「インターネットEDI」と呼んでいます。
2024年1月の固定電話網のIP化(ISDN回線サービス(INSネットのディジタル通信モード)終了)により、レガシーEDIからインターネットEDIやWeb-EDIへ多くの企業は移行済みかと思います。
| レガシーEDI | レガシーEDIは、通信手段に固定電話回線を用いる古いデータ交換の仕組みです。 |
|---|---|
| インターネットEDI | インターネットEDIは、インターネットを介してEDIを行う方法全般を指します。 Webブラウザ型Web-EDIやファイル転送型Web-EDI(「6.Web-EDIとは?」参照)も、インターネットEDIの一種です。 |
通信プロトコル
| レガシーEDI | JCA手順、全銀手順、全銀TCP/IP、FAX |
|---|---|
| インターネットEDI | JX手順、EDIINT AS2、ebXML MS、FTP、SFTP、HTTPS |
フォーマット
固定長、CSV、XML、PDF、JPEG、EXCEL、ZIP

スマクラのインターネットEDI「スマクラ EDI」は、発注・受注企業向けクラウド型のEDIサービスです。
さまざまな業種・業態、プラットフォーム、プロトコルを接続する、クラウド型のEDIシステムで、企業間のシステムを繋いだ連携基盤サービスとして、入力業務や通達業務の効率化を実現します。
6.Web-EDIとは?
Web-EDIとは、インターネットを介して取引先との商取引データを電子的にやり取りするシステムです。受発注、納品、請求などの業務プロセスを効率化し、企業間取引をスムーズにします。
従来のEDIシステムがVANや専用回線を使用していたのに対し、Web-EDIはインターネットを利用することで、より低コストで柔軟な運用を可能にしています。
Web-EDIはインターネットEDIの中に含まれていて、主に「Webブラウザ型Web-EDI」と「ファイル転送型Web-EDI」の2種類に分類されます。企業は自社のニーズや取引形態に合わせて適切なWeb-EDIを選択することができます。
| Webブラウザ型Web-EDI | Webブラウザ型Web-EDIは、インターネットブラウザを使ってEDIシステムにアクセスし、データのやり取りを行う方法です。 特別なソフトウェアをインストールする必要がなく、普通のウェブブラウザ(例えば、Google ChromeやMicrosoft Edge)を使って操作します。インターネットに接続できる環境があれば、どこからでも利用できるのが利点です。一方、Web画面のため手入力が多くなり、Web画面がサービス提供各社毎に異なるといったデメリットがあります。 |
|---|---|
| ファイル転送型Web-EDI | ファイル転送型Web-EDIは、専用のファイル転送ソフトウェアを使ってデータをやり取りする方法です。 データを一定の形式で作成し、そのファイルを送信します。この方法は、大量のデータを効率的に転送するのに適しています。ただし、専用ソフトのインストールが必要です。 |
Web-EDIの主な特徴として、導入コストの低減、運用の柔軟性、セキュリティの向上などが挙げられます。さらに、大容量データの処理、通信コストの削減、ペーパーレス化の促進など、多くの利点があります。これらの利点により、多くの企業がWeb-EDIの導入を検討するようになっています。
Web-EDIの導入を検討する際は、自社の業務プロセスや取引規模、取引先のニーズなどを総合的に評価し、最適なシステムを選択することが重要です。また、データの標準化や業務プロセスの見直しなど、EDI導入に伴う社内の体制整備も併せて行うことで、より効果的な活用が可能となります。
スマクラのWeb-EDIは、高品質かつ短納期で導入可能なクラウド型サービスで、一般企業向けの「スマクラ Web-EDI」および製造業に特化した「スマクラBDX 調達購買Web」を提供しています。これらのサービスを活用することで、契約企業様・取引先様双方の業務負荷軽減が図れます。