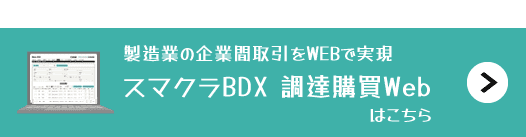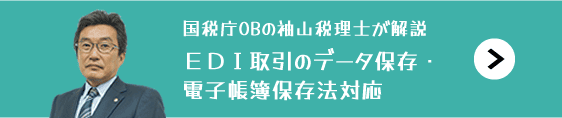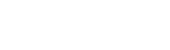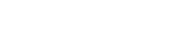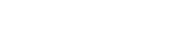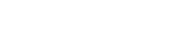EDIのメリットとデメリットとは?EDIを分かりやすく説明「EDIガイド」


EDI導入によるメリットと、一定の条件を満たしていなければデメリットも発生する場合があることについて説明します。
1.EDIのメリットとは?(EDI取引のメリット)
- 業務の自動化
- EDIを導入することで、以下のような業務を自動化できます。
- ●受発注書類の作成と処理: 注文書や納品書の作成、印刷、封入、送付といった人的業務が不要になります。
●データ連携: 受発注など取引に関わるデータ連携業務をすべて自動化できます。
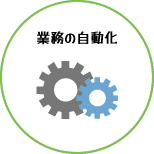
- ペーパーレス化・コスト削減
- EDIを導入することで、紙媒体でのやり取りを電子データに置き換え、ペーパーレス化を実現できます。これにより、以下のコスト削減効果が期待できます。
- ●受発注など取引に関わる郵送代、用紙代、印刷代の削減
●紙作業にかかる人件費の削減 - 取引社数が多い、あるいは取引頻度が高いほど、ペーパーレス化によるコスト削減効果は大きくなります。

- 業務スピードの向上
- EDIを導入することで、手作業で行っていた業務が自動化されます。これにより、注文データが出荷や納品の元データとして引き継がれるため、以下の効果が期待できます。
- ●出荷データや納品データ作成の手間や工数が大幅に削減されます。
●注文から商品納入までのリードタイムが短縮され、企業間取引の業務スピードが向上します。

- 正確性の向上・人的ミスの削減
- EDIを導入することで、以下の業務が自動化されます。
- ●受発注に関わる書類作成(注文書や納品書など)、印刷、封入、送付などの手作業
●伝票入力作業や受領したCSVファイルの連携作業 - 例えば、注文者が入力した発注データは、サプライヤーの基幹システムに受注データとして直接連携されます。これにより、以下の効果が期待できます。
- ●手作業による業務プロセスがなくなり、人為的なミスが発生しなくなります。
●数量の桁間違いやファイルの展開ミスなど、人的ミスを防ぐことができます。
●企業間で連携するデータの正確性が向上します。
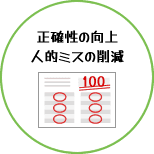
- サプライヤーとの連携強化
- EDIを利用し、サプライヤーと相互の基幹システム連携を実施することで、企業間取引に関する業務効率が向上します。
EDI取引の実施だけでも業務効率化やリードタイムの短縮といったメリットがありますが、さらにEDIに密接に連携したサプライヤーポータルと電子契約システムを同一プラットフォーム上に構築することで、以下のようなサプライヤーとの連携強化が期待できます。

受発注情報の連携・共有
●商取引情報に技術情報を付加することで、業務効率化が進みます。
●見積から注文段階で図面・仕様書のデータを付加して送受信することで、作業ミスの撲滅や検索・閲覧が容易になります。
●業務掲示板やお知らせ、取引先情報の自動収集などにより、受発注関連業務が円滑になります。
電子契約システムとの連携
●新規サプライヤーとのEDI開始には契約書の締結が必須です。
●EDI・サプライヤーポータル・電子契約システムが同一プラットフォーム上で連携していることで、契約締結からEDI取引開始までの一連の手続きをスムーズに進めることができます。
在庫状況の把握
●サプライヤーの在庫状況を把握することで、生産計画に基づいた発注オペレーションが可能になります。
●BCP対策(部品不足による業務中断リスク対策)にも有効です。
天災時の安否確認と供給可能状況の把握
●自動アンケート機能により、サプライヤーの安否確認と供給状況の把握が容易になります。
●倉庫や物流センターの状況を把握し、部品納入が可能かどうかを迅速に調査できます。これもBCP対策に寄与します。
法律・制度の改正情報の提供
●法律や制度の改正情報、カーボンニュートラルや人権に関する情報を提供することで、特に小規模企業のコンプライアンスの向上が期待できます。
●環境への貢献、人権の尊重、信頼関係の強化、競争力の向上にもつながります。
スマクラBDX調達購買Webは、EDI・サプライヤーポータル・電子契約などの機能を統合したクラウド型プラットフォームとして提供しており、サプライヤーとの取引を一元管理できます。
- 法制度対応の容易性
- EDIの導入により、取引に要する書類が電子化され、一元的に管理できるようになることで、「電子帳簿保存法」や「インボイス制度」といった法律・制度への対応が容易になります。
EDIシステムやEDIサービスには、これらの法律・制度に対応した機能を持つものもあります。
後者の場合、法律・制度に対応した機能の開発・保守の責任はEDIサービス・プロバイダー側となるため、法令遵守の点、および社内の情報システム部門の運用負荷軽減の点からも有用と言えます。
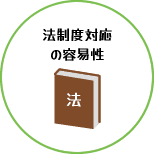
2.EDIのデメリットとは?(EDI取引のデメリットとは?)
- サプライヤーの導入ハードルが高い
- EDIシステムの導入は、サプライヤーが同じシステムを採用している場合にその効果を最大限に発揮します。
取引先の技術的対応が不十分な場合、従来の手作業のプロセスと併用する必要が生じ、データ互換性や標準の違いが問題になることもあります。そのため、サプライヤーとの調整や追加の開発が必要になる場合があります。
- 業務プロセスの変更
- 新規EDI導入やシステム刷新には、業務プロセスの変更が伴い、従業員の教育やトレーニングが必要となる場合があります。
- 費用対効果
- EDIシステムの導入には初期費用が発生し、ハードウェアやソフトウェアの購入費用、インフラ整備費用、導入コンサルティング費用などが含まれます。また、自社構築の場合、24時間365日の対応が必要となるケースも多く、導入後も運用サポートや保守に関するコストが継続的に発生します。
システムの不具合やトラブルへの対応、バージョンアップやセキュリティ対策の更新作業にも費用がかかります。
- システム障害のリスク
- EDIシステムに障害が発生した場合、業務に重大な影響を及ぼす可能性があります。
システムのダウンタイムやデータの不整合が生じると、取引先との連携が滞り、納期遅延や誤出荷のリスクが高まります。これを防ぐためにバックアップ手段や代替業務プロセスの準備が必要ですが、そのための準備や運用コストも無視できません。
これらの課題を考慮すると、スマクラのようなクラウドベースのEDIサービスの導入が効果的な解決策となります。専門知識と最新技術の活用、初期投資とランニングコストの削減、柔軟性の向上、リスク管理の改善が可能になります。さらに、多様な業界標準に対応し、取引先との円滑な連携を支援します。スマクラの導入により、EDIシステムの課題を効果的に解決し、業務効率の向上とコスト削減を同時に達成できる可能性が高まります。