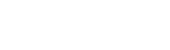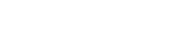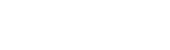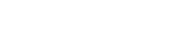EDIの導入方法は?EDIを分かりやすく説明「EDIガイド」


EDIの導入方法には、主にオンプレミス(自社構築・運用)とクラウド(SaaS)の2種類があります。

1.オンプレミスとは?
自社にサーバーを構築し、自社で運用を行う方法です。
メリットとしてはカスタマイズの制限がないこと、自分たちの資産となることなどが挙げられます。
逆にデメリットとしては、初期費用が高額になること、セキュリティ投資などが別途必要になること、運用負担が大きいことなどが挙げられます。
企業のIT部門にとっては、システムの開発や保守・運用に相当の手間がかかりますし、システムを作り上げ、保守・運用を担ってきた担当者以外は中身がわからず、接続先の追加やEDIと基幹システムとの連携などが行えないといった属人化の状況に陥るリスクもあります。
2.クラウドとは?
インターネットを通じて、提供会社のサービスを利用する方法です。
メリットとしては初期費用が比較的安価であること、セキュリティの投資は提供会社が行うこと、運用負担を軽減できることなどが挙げられます。また、財務上はサービス利用料としての計上となるため、資産効率の改善を行うことができます。
企業のIT部門は、EDI業務を支えるシステムインフラの整備や保守・運用から解放され、EDIというミッションクリティカルな仕組みの可用性や24時間365日の安定稼働を手間をかけずに確保できる可能性が大きくなります。また、人的リソースを、より戦略的で働き手のモチベーションが高いレベルで維持できるIT業務に割り振ることが可能になります。
逆にデメリットとしては、一般的にカスタマイズに制限があること、他システムとの連携に制限があることなどが挙げられますが、スマクラは柔軟に対応しています。
オンプレとクラウドを比較した場合、ハウジング費用や運用にかかる人的コストまで考慮すると、長期間で見てもクラウドの方がコスト面でも優位です。

インターネットEDIやWeb-EDI、ECALGA、流通BMS、FAX配信など、幅広いEDIニーズに柔軟に対応し、各種多様なプロトコル変換やマッピングに対応可能なSCSKのクラウド型統合EDIサービス「スマクラ」は、EDIにおけるシステムの開発から構築、導入・保守・運用に至るまでのサービスが包括的に提供されるソリューションです。
EDIに関する豊富な運用実績とノウハウを有し、製造や流通の商習慣にも精通する専任チームが、システム移行や保守・運用、ヘルプデスクなどの業務にあたります。
3.アウトソーシングのメリットとは?
EDIシステムをEDIサービス・プロバイダーにアウトソーシングすることで、企業は多くのメリットを得ることができます。以下の表は、EDIアウトソーシングによって得られる主要な利点を示しています。
| コスト削減 | 自社構築でEDIシステムを構築・運用するよりも、アウトソーシングによって初期導入費用や運用コストを大幅に削減できます。 |
|---|---|
| 専門知識の活用 | EDIサービス・プロバイダーは専門的な知識と経験を持っており、システムの設計や運用を効率的に行うことができます。 |
| 迅速な導入 | アウトソーシングすることで、迅速にEDIシステムを導入し、運用を開始することができます。自社での開発や設定に時間をかける必要がありません。 |
| システムの維持管理 | EDIサービス・プロバイダーがシステムの保守・管理を担当するため、内部リソースを他の重要な業務に集中させることができます。 |
| セキュリティ強化 | EDIサービスは最新のセキュリティ対策を導入しており、データの保護や不正アクセス防止に効果的です。 |
| 柔軟なスケジューリング | 業務量の変動に応じてシステムのスケールアップやスケールダウンが可能で、ビジネスの成長に柔軟に対応できます。 |
| 導入・運用サポート | EDIサービス・プロバイダーから、導入時の各種資料のテンプレートの提供や導入教育の提供が可能です。 運用は通常24時間365日のサポートを提供しており、トラブル発生時にも迅速に対応できます。 |
| 法令順守のサポート | EDIサービス・プロバイダーが法的要件やコンプライアンスの遵守を支援し、常に最新の規制に対応できるようにします。 |
| 高い可用性 | EDIサービスは高い可用性と信頼性を持っており、業務の中断を最小限に抑えます。 |
| 業務効率の向上 | EDIサービス・プロバイダーに委託することで、EDI業務の効率が向上し、リソースを本業に集中させることができます。 |
4.クラウドとオンプレミスの比較
EDIシステムの導入を検討する際の、クラウド型とオンプレミス型の主要な比較ポイントをまとめたものです。各項目について、クラウド型とオンプレミス型それぞれのメリット・デメリットを〇、△、×で表しています。この比較表を参考に、貴社のニーズや状況に最適なEDIシステムの選択にお役立てください。
| 項目 | 比較ポイント | クラウド | オンプレミス |
|---|---|---|---|
| 初期費用 | □ 初期費用を抑えられるか | 〇 | △ |
| 月額費用 | □ 月額費用を抑えられるか | 〇 | △ |
| 適用業務範囲・提供機能 | □ 顧客が必要としている適用業務範囲とその機能を有しているか | 〇 | △ |
| 運用サポート | □ 運用サポートはあるか □ 事業継続性が確保されるか |
〇 | × |
| 堅牢で実績のあるEDIインフラ | □ EDIのインフラ環境のセキュリティは担保されているか □ 顧客の運用業務負荷が軽減できるか |
〇 | △ |
| 障害リスク | □ 障害発生時に低コストで事業継続性が確保されるか □ 障害発生リスクは少ないか |
〇 | △ |
| セキュリティの管理・運用 | □ 自社責任のセキュリティの管理・運用は、不要か | 〇 | △ |
| 通信手順 | □ 標準的なインターネットEDIの通信プロトコルや利用頻度が高いフォーマットに対応しているか | 〇 | △ |
| 機能拡充 | □ 法改正に対応しやすいか □ 通信手順の追加に対応しやすいか |
〇 | × |
| 導入しやすさ・廃棄のしやすさ | □ システムを導入しやすいか □ システムを廃棄しやすいか |
〇 | × |
| 接続先追加の柔軟性 | □ 従量制で、かつ必要なタイミングで対応できるか | 〇 | × |
| 保守・運用の人員確保 | □ 保守・運用の人材が確保されているか □ 保守・運用業務の属人化のリスクはないか |
〇 | × |
| 資産管理 | □ 固定資産税が発生しないか □ 会計処理に手間がかからないか |
〇 | △ |
| サプライヤーポータル機能(情報管理基盤) | □ サプライヤーとEDI業務に関わる情報管理、業務支援、コミュニケーションツールが整備されているか | 〇 | △ |
5.クラウドとオンプレミスの法制度対応の違いは?
EDIシステム・EDIサービスの法令・制度への対応(システム・サービスの改修)は、自社構築を選ぶか、EDIサービスの利用を選ぶかによってEDIを導入する企業の責任範囲が異なります。
| 項目 | クラウド | オンプレミス |
|---|---|---|
| 法令・制度への迅速な対応 | EDIサービス・プロバイダーにて法令・制度対応のための専門要員を抱えているため、迅速な対応が可能。 法令・制度へ対応できているかどうかの責任はEDIサービス・プロバイダーにある。アップデートもEDIサービス・プロバイダーの責任で実施する。 |
EDI導入企業側で法令・制度対応のための専門要員を確保できないリスクがある。通常は情報システム部門が担っていて、他業務もあることから、迅速な対応が行えないリスクがある。 法令・制度へ対応できているかどうかの責任はEDI導入企業にあり、アップデートもEDI導入企業の責任で実施する。 |
| 法令・制度に対応するためのシステム・サービス改修費用 | 標準サービスでの利用の場合は、共同利用が前提となるため、1社負担よりも安くなる。 個社機能部分への改修の場合は、個社負担となる。 |
EEDI導入企業の全負担となる。 |
| 業界および複雑な法令・制度に対応するための最新の技術とノウハウなど専門知識 | EDIサービス・プロバイダーにて専門要員を確保している。 EDIサービス利用企業はEDIサービス・プロバイダーのサポートを受けられる。 |
自社要員にて確保する必要がある。 関連情報もEDI導入企業で取得する必要がある。 |
| 法令・制度に対応するためのセキュリティの強化 | EEDIサービス・プロバイダーは高水準のセキュリティ対策を実施しており、データの安全性が確保されています。 特に法令に基づいたセキュリティ要件を満たすことができます。 |
EDI導入企業の全負担となる。 予算次第のセキュリティレベルになりがち。 セキュリティ要件適用の確認はEDI導入企業の責任となる。 |
| 法令・制度対応のシステム改修に耐えられるスケーラビリティ(取引データの増加や新たなサプライヤーの追加、業務フローの複雑化などに対するシステムの効率的な拡張能力)と柔軟性の確保 | スケーラビリティと柔軟性の確保の責任は、EDIサービス・プロバイダーにある。 | スケーラビリティと柔軟性の確保の責任はEDI導入企業にある。 |